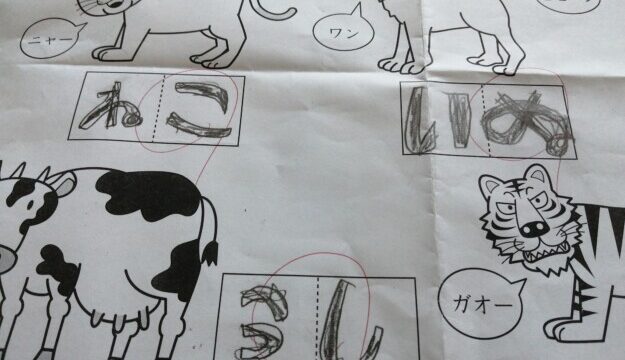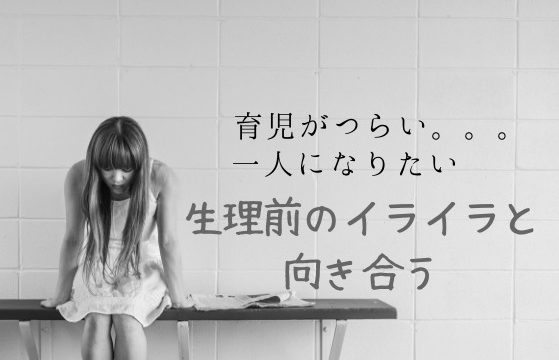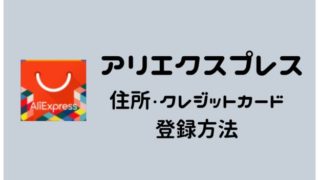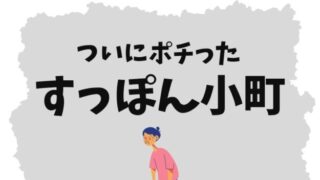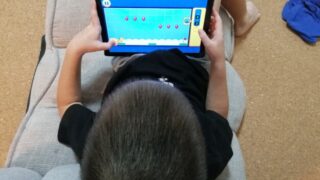本記事では息子の発達が心配になってから発達相談に向かった経緯について綴らせていただきます。
もうすぐ3歳になる息子ちゃん。
1歳半くらいから少しずつ周りの子と違う気がして発達が気になり、2歳半から発達に少し心配がある子が通う区の親子教室に通っています。
専門の先生が来てくれて、月に2回、親子一緒に楽しく参加させてもらっています。
通い始めて4ヶ月になりますが、息子は4ヶ月前とは見違えるほど言葉も増えたし、落ち着いてきたようにも思います。
「発達障害かも。。」と漠然と不安に思っていた時期があるのですが、
私は勇気を出して相談してみて良かったと思っています。
不安に思うことがあってもスルーしてしまうことってあると思います。
でも、私は向き合ってみて良かったと思うので、そんなケースの一つとして、私が息子の発達が心配になり相談してから現在に至るまでの経緯を綴らせていただきます。
発達障害という言葉と向き合う
1歳半あたりから「あれ?ちょっとうちの子違う??」と思うことはあったのです。
子育て支援センターでの読み聞かせや体操などに参加しても、1人走り回っていたり脱走したり。
男の子はこんなもんだと思っていましたが、意外と同じ年の子はもう少し落ち着いていたり、お話も上手だったりすることに驚いたり。
そんな感じでも2歳までは特に気にせずやってきました。
ただ、2歳になっても
- 話す言葉は10単語ほど。
- 人見知りがない。
- 誰にでもついていく。
- プレ幼稚園は脱走する。
- スーパーで消える。
- ものすごい偏食。
- 食事も3口食べたら席から離れる。
- 基本ずっと走っている。
- 外で靴を脱ぎたがる。
「何か策はないだろうか?」と検索する度に「発達障害」という言葉が。
子どもなんてそんなもんだろうと考えていたので「また出た。発達障害」と思っていました。
ところが息子が2歳過ぎた頃。
ふとしたきっかけで息子のバイバイが逆さま(手のひらが自分の方に向いている)であることについて調べてみたところ「自閉症に見られる特徴の1つ」と。
そして早産児にも発達障害が多いという情報もあり(息子は1000gほどで生まれています)
さすがに気になり始めました。
特にADHD(注意欠如・多動症)の特徴が当時の息子に当てはまることがたくさんで。
そこからは、発達障害のことばかり調べていました。
調べていく中で、
発達障害は早期発見、早期療育が大切
ということもわかってきました。
だんだん不安でじっとしていられなくなって。
「ただ不安に思っているよりもちゃんと向き合おう。」と意を決して相談することにしました。
子どもの発達が気になる時はどこに相談すれば良いのか?
息子は早産だったので、生まれた病院で定期的にフォローアップ健診を受けています。
なので、自分で相談できる場所を探して相談に行きました。
子供の発達に不安がある場合、まずはどこに相談するか。
一般的には以下の施設で相談を受付けているようです。
-
保健センター
-
小児科
-
子育て支援センター
-
発達障害者支援センター
私の場合は、区の保健センターへコンタクトを取りました。
子育て支援センターで相談をしたこともあるのですが、子育てのアドバイスを受ける感じになってしまい「発達障害ではないか?」の不安は解消されませんでした。
また、うちの地域の発達障害者支援センターは紹介を受けて更に細かく診る場所の意味合いが強く、直接コンタクトを取って診てもらえるのかはわかりませんでした。
まだ息子を客観的に診てもらっていない状況で直接連絡を取るのはハードルが高かった。
最初にコンタクトを取りやすいのが、地域の保健センターか小児科かと思います。
1歳半検診、3歳検診が近いのであれば検診の際に小児科の先生に相談するというのも1つです。
保険センターの発達相談の流れ
保険センターへ相談した際の流れについて綴ります。
面談予約を取る。
まずはお住まいの保険センターへ面談予約を取ります。
私の場合は、いきおい余って(笑)保健センターへ直接出向いて「息子が発達障害かもしれない」と心配している旨を伝え、そういった相談やサポートの機会があるかを聞きました。
私の住む地域では、担当の保健師さんが地域ごとに決まっています。担当保健師さんとまずは面談をすることになり、後日面談予約を取るよう促されました。
私は直接出向いてしまいましたが、まずは電話で相談、予約を取るのが一般的なようです(あたりまえですね。すみません)
1度目の面談。準備不足で終わる。
最初に面談を受けた際は、30分程度保健師さんとお話させてもらいました。
- 話す単語が15個ほど。
- バイバイが逆さまである。
- 落ち着きがない。
- 食事に興味がない。
- こちらが話していることが伝わっているか正直自信がない。
- 常に走っている。
2歳1か月(修正1歳11ヵ月)の時点で、上記のことが気になる旨を伝え、息子が遊んでいる姿を見てもらいました。
その時点では、
「言葉が15個出ていれば十分」
「遊び方を見ていてもちゃんと意味のある遊びをしているし問題ないように思う」
という感じでした。
ただ、明らかに私の準備不足で伝えきれず。不安は拭えず。
保健師さんに話す言葉や日々の生活について質問を受けても、細かく覚えているわけではなかったので、曖昧にしか返答ができませんでした。
息子も慣れない場所だと、いつものように走り回ることもないし、大人しく游ぶんですよね。
- 「問題ないように思う」という回答も、いつもの息子を見て言ってもらったわけではない。
- 私も準備不足で細かい部分を伝えきれていない。
発達障害と診断してほしいわけではないのですが、モヤモヤしたすっきりしないような気持ちで1度目の面談を終えました。
2回目の面談。やっと伝わりホッとする。
経過観察ということで、1度目の面談から3か月後に再度保健師さんの面談を受けました。
2度目の面談は、1時間以上息子が遊んでいる姿を見てもらいながら、気になっていることなどをお話しました。
1時間以上一緒に過ごしていると、息子も慣れてきていつもの調子が出てくる。
私も、気になっていること、最近の様子などを細かくメモにまとめていきました。
長い時間を息子と過ごしてもらうことで、「お母さんのおっしゃっていることがよくわかりました。」と言ってもらえました。
「やっと伝わった。」と思ったのと同時に、次に進めるような気がしてホッとしました。
「親子教室というものがあって、そこでもう少し息子さんのことを見ていきたいのですがどうですか?」と保健師さんから言われて、「ぜひ参加させてください」と即答しました。
親子教室とは何なのか?
親子教室とはいったいどんなところなのか。
うちの地域の場合は、
区の保健センターが実施している言葉が遅い子や、発達に少し不安がある子に、遊びを通じて発達を促す活動をする場所
ということでした。
費用は無料。誰でも参加できるわけではなく、事前に面談をして必要と判断された場合のみ参加できます。
2週間に1回。合計10回の活動を行います。
そのまま卒業することもあれば、更に細かく診る必要があると判断された場合は、専門機関などの紹介もするということでした。
親子教室での発見
親子教室に通い始めてびっくりしたことがあります。
ショッピングモールや公園で、息子と同じ年齢で同じくらいの言葉数で、落ち着きがない子に出会ったことが何回かあるんですよね。
ママと少し話して「うちも言葉が遅くて落ち着きがないんです~」なんてお互い言いながら「うちの子だけじゃないんだ」とこっそり安心していました(ごめんなさい)
が、親子教室でことごとく再会(笑)
あ、〇〇で一度一緒に遊んだことがありますよね?
ということが何回かありました。
今まで「息子と同じ感じの子いるじゃん」と思っていましたが、やはり親子教室で再会するにつれて、やっぱり客観的に見ると「グレーっ子なんだなうちの子」と思えるようになってきました。
親子教室の効果
息子が親子教室に通い始めて4ヶ月が経ちました。
脱走しようとするし、走り回って全然活動に参加しないし、話も聞いているのか聞いていないのかわからないし、何より私も疲れるし。
活動も、アンパンマンの歌に合わせて踊ったり、走り回って急にストップしたり、
素人目には、特別な活動のようには見えなかったんですよね。
意味あんのかな??と正直思うこともありました。
2歳7ヶ月時点で話す単語が30単語ほどだったのが、1ヶ月ほどで一気に100単語以上になりました。
更に2ヶ月経った現在は「オオキイクルマ」など2語文も出るようになっています。
ここ3ヶ月で、30単語⇒2語文まで一気に言葉が爆発しました。
そして言葉が増えると同時に、手をつないで歩けるようになったり、ちゃんとお話しして聞かせたら理解してくれることも出てきた。
靴もちゃんと履いてくれるように。
明らかに以前の野生児のような状態から少し変わってきました。
何より集団で踊ったり、絵本を聞いたりすることがあまり好きではない息子が、最後まで参加できるかどうかは別として(笑)毎回楽しそうに通うようになりました。
気になっているのなら、向き合った方が良いと私は思う。
息子の発達を気にしていた頃の私は「発達障害の特徴」を見て、息子に当てはまらないかどうかばかり気にしていました。
ただ、発達障害は「この特徴なので発達障害です!」というハッキリ数値化できるようなものではありません。
そして誰にでも発達障害っぽいところってあると思うのですが、それが、性格なのか障害なのかの判断に至るポイントは
「生活に支障が出る程度であるかどうか」のようです。
そんなの、素人がインターネットを見ているだけでは判断できないですよね。
発達障害って診断されたらショックだし、自分の子は大丈夫と思いたい。
でも、相談してみないと不安なまま。
- 発達障害でなければ、それはそれで安心できるし。
- 発達障害なのであれば、できることをやっていくしかない。
相談してみて悪いことは一つもないと私は思いました。
お子さんの発達が気になっているのであれば、専門の方に相談して見てもらったほうが、やはりモヤモヤはスッキリします。
気になっているということは、今の時点ではそういう性質がやっぱりその子にはあるということだから。
そしたら、上手に対処できる術を早めに学べた方が、子どもにとっても親にとっても良い方向にいくのではないでしょうか。
最後に
つらつら書いてきましたが、「もしお子さんの発達に少しでも不安があるのであれば、相談してみた方が良い」というのが私の考えです。
ただ、相談する場合。保健師さんの面談でも思いましたが、なかなか短い間では、子どもの気になっていることをすべて理解してもらうことは難しいです。
伝わらないこともあるかもしれませんが、納得いくまで伝えないとモヤモヤは落ち着きません。
日々の生活で気になることや、話す言葉などをメモするなど準備して面談に臨まれることをお勧めします。
私だけかもしれないですけどね、、準備しないで面談とか受ける人は(^^;)
あと、本気でちゃんと専門家と繋がって相談したいと考えている場合は、ちょっと頑張ってアピールした方が良いです。
「うちの子大丈夫ですかね?」というスタンスだと、どこで相談しても基本的には「このくらいの子はこんなもんよ」で様子見になることがほとんどです。
長々とありがとうございました。
▽合わせて読みたい
親子教室終了後、児童精神科の先生に診てもらい発達障害の特性ありで療育に通うことになりました。
そのあたりの気持ちを綴っています。